
私が今学んでいる教科書の『シナリオの基礎技術』でテーマとモチーフの役割が理解できると、物語を書く手順がとても良く納得できたので、今回はその学びについて書いて置きたい。
前回に、テーマは「自分の価値観を伝えるのが目的」、モチーフは「どのような手段(表現、設定)で伝えたら最も効果的なのか」ということを学んだ。
テーマとモチーフは物語の重要な要素というだけでなく、物語の書き方、書く手順にも影響する大切な考え方だということを今回学んだ。
テーマとモチーフのことをいい加減に考えていた私にとって、テーマとモチーフから導き出される書く手順が、その理由も含めてとても納得いくものに感じられた。
物語を書く手順に試行錯誤していた私には、これ以外にないと思えるほど合理的で説得力のある書き方に思えた。
前回学んだテーマとモチーフの選択も含めて、物語を書く手順をスタートからまとめてみる。
予備知識として、物語の構成方法として、「起承転結」という考え方を用いていることを断っておく。
1. テーマを選ぶ
人は誰でもその人なりの価値観というものを持っている。それは生まれてから今まで生きてきた中で形成されたもので、多くの人と共感できるものもあれば、その人独自の価値観もある。
小説にしろ演劇、映画にしろ、物語で何かを表現したいという欲求は、自分の価値観を多くの人に訴えたい欲求に基づいている。
今自分が最も関心を持っている価値観、最も訴えたい価値観を多くの人に伝えたい、それがテーマになる。
自分の価値観を人に伝えるという目的を持ったものがテーマという概念だ。
物語を書く手順の一番最初の工程は、テーマを選ぶことから始まる。
後でわかるのだが、テーマとは物語の到達点であり出発点を決めるものでもあるのだ。テーマが決まらなければ物語は始まらないし、目的も定まらずに迷走してしまう。
だからテーマを選ぶ工程は物語を書く手順の一番最初になくてはならない。
前回も書いたが、価値観は各自が既に持っている。だからテーマを考えることで苦しむとか、テーマが見つからないということはない。なぜなら、なんらかの価値観は誰もが既に持っているいるのだから。自分の価値観の中から何を選ぶかという作業があるだけだ。
説明を分かりやすくするために、今回テーマとして「人間は人を殺してはならない」ことを伝えたいとする。
2. アンチテーゼを考える
物語が面白いのは、主人公が敵や邪魔者から攻撃や妨害されたりして、対立や葛藤が生まれるからだ。
アンチテーゼとはテーマの価値観と対立する価値観だ。今回の場合でいえば、「人間は状況によっては人を殺すことが許される」みたいになる。
テーマとアンチテーゼが争いながら物語は展開していく。だからこの2つが最初に決まっていないと物語は進まない。
アンチテーゼはテーマを引き立たせるための必要悪のようなものだ。
3. 物語の「転」を考える
テーマとアンチテーゼの対立が極限に達したところで起こるのが転のパートだ。
今回のテーマ「人間は人を殺してはならない」と、「人間は状況によっては人を殺すことが許される」というアンチテーゼとの対立が極限に達したクライマックスの状況を考える。
なぜいきなり転から考えるのか?私もそう思った。教科書の説明によれば、「転とはテーマそのもの」という理由からだ。
なるほど、テーマとは最も伝えたい価値観であり、転の役割もその価値観を感動的に使えるパートであるからだ。
だから転とは、テーマを具体化した場面ということになる。言葉で「人間は人を殺してはならない」としたのでは感動は生まれない。言葉で説明するのではなくて、他の手段でテーマを伝えなければならない。
言葉でテーマを伝えないためにアンチテーゼとの対立がある。両者の対立を描くことでテーマを伝えることができる。
転ではテーマがアンチテーゼを克服しなければならない。そのような状況の場面をイメージすることが転では求められる。
今回の場合は、「状況によっては人を殺しても良い」という価値観を、「状況によらず人を殺してはならない」という価値観が打ち勝つ場面を具体的にイメージすることになる。いくつか考えてみる。
- 戦場で捕虜にした敵の少年兵を、「こんな奴を生かしておいてはためにならん、撃ち殺せ!」と命令する上官に逆らって過酷な懲罰を受けた青年兵は復員後警察官になった。戦後の混乱した中で暴力組織の下っ端として悪事を働いていた不良少年を、その警察官は正当防衛で射殺してしまうが、その少年は元上官の一人息子だった。「どうして殺した!」と責める元上官に、元部下の警察官は「こんな奴を生かしておいてはためにならんからですよ」と答える。
- 強盗殺人の罪で死刑の執行が近いとされた死刑囚がいた。その死刑囚は無罪を主張したり再審を要求することもなく、静かに執行の日を待っていた。その死刑囚にはたった一人の身寄りである弟がいた。その死刑囚は、実は弟の身代わりになって罪をかぶったのである。歳の離れた弟が悪の道に走ったのは、親代わりで厳しく接してしまった自分のせいだと悔やんだ兄が、罪滅ぼしの心で冤罪を受け入れたのだ。死刑が執行された日、刑務所の塀の外で弟は泣き崩れた。
初めの方の工程で転を考えるのは難しいのではないかと私は思った。しかし、テーマとアンチテーゼが決まっていると、両者の対立を具体化する作業は意外と苦にはならないと感じた。
テーマもアンチテーゼも抽象的な価値観なのだが、反対の価値観が対立しているためか、具体的なイメージが想像できるのだ。抽象的な概念を具体化するのは、案外難しいことではないのかもしれない。
考えてみると、この転のパートこそがモチーフを考える工程そのものだとわかる。どうしたらテーマを効果的に伝えられるかを意識しているからだ。
4. 起を考える
転のクライマックスをイメージした時、かなり具体的な状況を想像することができた。具体的な想像によって、起に必要な設定が容易になる。
教科書に従えば、起には「天・地・人」の3要素が必要になる。
- 天:時代・状況の設定
- 地:場所の設定
- 人:登場人物の設定
私が想像した一つの転のイメージを例にとれば、
- 天:戦中・戦後の時代
- 地:異国の戦場と戦後の内地
- 人:主人公の青年兵(警察官)、敵役の上官、異国の少年兵、上官の息子
転が先にイメージできていると、天地人が具体的にイメージできるし、物語に不必要な要素や設定を防ぐことができる。
5. 承を考える
教科書の説明で、承のパートをとても長くとっていることに驚いた。シナリオの全体を8つのパートに区分している。
- 1: 起
- 2,3,4,5,6:承
- 7:転
- 8:結
承を長くとっているのは、物語の発端から転のクライマックスへ向かっていく過程の中に、対立や葛藤のドラマを描くことを重視しているからだろう。
物語の成否は、承の工程でのドラマの盛り上がりにかかっていて、説得力を得るにはそれだけ多くのエピソードを必要としているとの認識があるからだ。
テーマとアンチテーゼの対立するエピソードが、次第に山場に向かってエスカレートしていくように描くのがこのパートの役割だ。
私の想像した物語を例にとった場合、承はこんな感じをイメージしてみた。
- 承1:正義感があり優しい青年が招集されて中国内陸の部隊に配属され、古参兵から理不尽にしごかれる。
- 承2:軍隊生活になれた頃に新兵が入ってきても、青年だけは自分が先輩から受けたしごきを新兵に加えなかった。
- 承3:南方の激戦地から転任してきた上官は、青年の軍人らしからぬ態度が気にいらなかった。
- 承4:上官に気に入られたい仲間の兵隊の密告によって、青年は戦意に欠ける嫌疑をかけられ制裁を受ける。
- 承5:戦況の悪化によって余裕のなくなった部隊は、戦闘員や民間人の区別なく殺戮していった。
ここでもテーマ、アンチテーゼ、そして転のクライマックスが決まっていることによって、その山場に向かって何が必要かがわかっているので、承のエピソードを考えやすく感じることができた。
6. 結を考える
私はこれまで転と結の区別があいまいだった。転でテーマを伝えてしまった後、何を付け加える必要があるのだろうと思っていた。
新たに理解したのは、結とは思っていた以上に短い場面であるということだ。
転で伝えたかったテーマを印象付けるエピソード、あるいはテーマの余韻を残すようなエピソードが描ければ良いということだ。
私が想像した物語の例でいえば、元上官の息子を射殺してしまった警察官は、正当防衛とはいえ命を奪ってしまったことを悔やみ、元上官の息子の墓前に手を合わせて許しを乞う。その姿にテーマの余韻を託す形で終わる。
今回の学びの感想
教科書では、アンチテーゼを転や起の後に考えるようにしている。しかし、私の考えではアンチテーゼはテーマのすぐ後に考えた方が良いと思った。
転のクライマックスや、起の天地人を考えるためには、状況や場面が具体的にイメージできないと作れない。
テーマとアンチテーゼがはっきりしていると、その対立関係の緊張によって転のクライマックスを具体化できる。そして起の天地人も自動的に設定できることになる。
この教科書で学び始めてから、テーマの重要性がますます大きく感じられるようになった。
テーマから物語作りの工程が始まるという意味だけでなく、テーマとは自分の価値観が試される重要な要素であるからだ。
物語を書くことは、自分の価値観を人に問うことと等しいということだ。
参考文献:
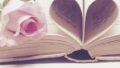

コメント