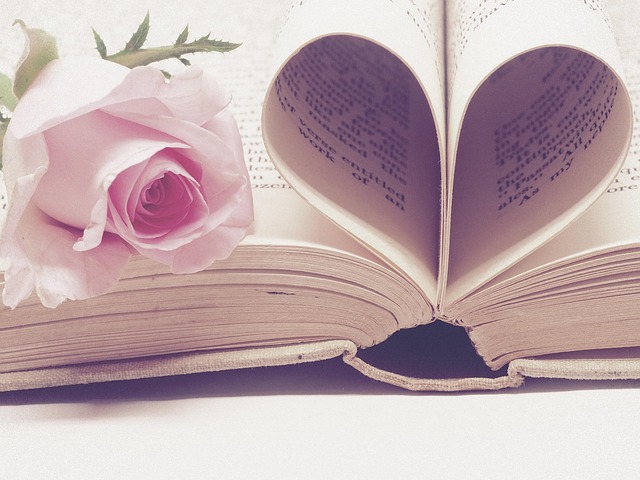
私は現在『シナリオの基礎技術』(新井一 著)という本でシナリオの勉強を始めたばかりだ。
今回学ぶのは、シナリオにとってのテーマとモチーフについてだが、この2つはシナリオに限らず小説でも演劇でも共通した要素だ。
テーマとは何か? モチーフとは何か? 改まって質問されて明確に答えられるだろうか?
なんとなくなら私も知ってるつもりだったが、それが正しいのかもあやふやだし、分かりやすく説明するとなると、自分でも良く理解していなかったことに気づく。
今回、この本を読んで具体的にというか、感覚的にというか、とても腑に落ちて理解できたのだ。
テーマは目的、モチーフは手段だった
私は今まで、小説とか映画とか演劇など物語にとってのテーマとは、「愛」とか「勇気」とか「死」とか、何か大きなこと、漠然とした抽象的なことを指す言葉だと思い込んでいた。
だから、「この小説のテーマは”友情”だ」とか「あの映画のテーマは”希望”だ」ぐらいに考えていた。目に見えない抽象的な価値みたいなものだと思っていた。
それは全く見当違いではないが、私はテーマの半分しか理解していなかったことがわかった。
この本を読んで、「テーマとは目的」 、「モチーフは手段」 なんだということが理解できた。
この本ではとても分かりやすく説明している。簡単に紹介しよう。著者にならい、私も物語風に説明する。
地方からシナリオライターになろうと東京に出てきた青年がいる。
青年は働きながら養成所に通い、シナリオの勉強に励んでいたが、お金に困るようになって、田舎の父親にお金の工面を頼むことになった。
青年は父親に手紙を出そうと思った。しかし、ただ「お金を送って欲しい」では説得できないと思った。
そこで青年は父親の感情に訴えるため、いかに青年が苦しいい状況にあるかを伝える必要があると考えた。
青年は風邪をこじらせて入院しなければならなくなり、その費用が予想以上に多くかかり、払えそうもなく困っている、という窮状を訴えた。
この青年の短い物語の中に、テーマとモチーフが含まれている。
「お金を送ってもらう」という目的がテーマで、その目的を達成するために「入院費が払えない窮状」を訴えるという手段がモチーフだ。
テーマは目的、モチーフはその手段。 この青年の例え話はとても分かりやすくないだろうか。
私がテーマを、”愛”だとか”友情”だとか大雑把にとらえていたことが不十分なのが良くわかった。
例えば、”愛とは自分の要求を満たすものではなくて、相手の幸せを無条件に願うものだと伝える”というように、何が目的なのかまで明確にしておかなければならなかったのだ。
モチーフについても、私のこれまでの認識は曖昧だった。モチーフとは、目的を効果的に実現させるための表現手段、相手にどう伝えたら最も効果的か、どのように表現すれば相手の心を動かせるか、という表現方法のことだったのだ。
だから青年の例でいえば、お金を送ってもらいたい目的は同じでも、モチーフはいくつもあり得ることになる。
- 仕事中に同僚に怪我をさせてしまったことを訴える。
- 友人の借金の保証人になってトラブルになったことを訴える。
- 最後のチャンスだと決意して働く時間を創作に打ち込みたいことを訴える。
テーマという目的は一つでも、相手(読者や観客)に訴えかける表現手段、表現方法は選択できる。もっとも効果的だと思うもので表現するのがモチーフだ。
私が調べたところ、モチーフ(motif)の語源とmove(動かす)の語源は通じているようだ。だから、相手の心を効果的に動かす(感動させる)手段、方法がモチーフと考えれば理解しやすいだろう。
アイデアとはモチーフをブレインダンプすることなんだ!
先の例で、お金を送ってもらう目的(テーマ)のために、入院費の支払いに困っていることを訴えること(モチーフ)を考えたように、目的(テーマ)のために手段(モチーフ)を考えることがアイデアを出す作業と言える。
この本でもモチーフを思い浮かぶ限り絞り出すことを勧めている。
ここまでで、私は自分の物語の作リ方が逆の順序で行なわれていたことに気がついた。
私はモチーフを先に探して、そこから導き出されるテーマを決めていたように思う。
身の回りの物や事、世間の話題、自分の記憶などの中から、心に引っかかることや、心を動かされたものを探して、そこからテーマを考えていた。
つまり、宛もなく何でもいいから心に触れるものを探すことを先行するので、それが見つからない限り物語を作り始められなかった。
それに比べて、テーマからモチーフを考える流れは、とても合理的に思えた。
テーマもモチーフ同様に宛もなく探し回るように見える。しかしそうではない。テーマというのは普遍的な価値を伝えることが目的だ。普遍的な価値というのは探し回らなくても既に眼の前に揃っているのだ。
愛、友情、死、生など普遍的な価値はいくらでも眼の前に準備されている。
それらの中から、普遍的な価値の何をどうしたいかを決めればテーマになる。だから、テーマとは探し回るのではなくて選択なのだ。今の自分にとって何が最も価値があり、その価値をどうしたいかを選択することがテーマを決める作業になる。
例えば、今の自分にとって「信じる」ということが最も関心のある価値だとして、「信じた人に裏切られたとしても、信じ続けることの美しさを伝えたい」が目的になりテーマが決まったとする。
そのテーマを伝えるのに、一番効果的に表現するにはどうするのが良いかを考える。モチーフの選択だ。例えば、
- 親友だと思っていた友人が、一緒に受けた大学に友人だけ不合格になって不仲になるが、避け続ける友人に以前と変わらぬ友情を諦めなかった主人公と和解する物語。
- お人好しの主人公が、友人に何度もお金を貸しては裏切られ続けるが、それでも疑うこと無く友情を信じている主人公に、友人は自分の罪の深さに改心して許しを乞う物語。
- 友人に恋人を奪われた主人公が、当初の二人を恨む気持ちを醜いものと悟り、欲望を抑制して誠実に生きることが心安らぐ生き方だと信じ続け、友人に捨てられた恋人が主人公の愛に気がつく物語。
内容の出来は別として、目的としてのテーマが先にあると、それをどう訴えるかを考えるモチーフをブレインダンプする流れは、とても無理なく自然にできる。
テーマが明確だと、モチーフも具体的にいろいろ思いつくことが可能になる。なにより作業が楽に感じる。
普遍的なテーマは自分の価値観と連動する。自分の価値観は既に決まっている。だからテーマを選ぶのは難しいことではない。
テーマが決まれば、それを表現する手段としてのモチーフは自然に生まれ出てくる。
物語のアイデアが出てこないとしたら、テーマが明確に決まっていないからだと思う。テーマが先で、その後にモチーフという順番だ。
そして、テーマは自分の中にある価値観の中の選択で、その後にモチーフを頭の中から絞り出す(ブレインダンプ)アイデア出しの作業という流れが、物語の作り方の最初の工程になる。
この工程を長い間逆に考えていた私にとって、この気づきは大きな発見だった。
参考文献:


コメント