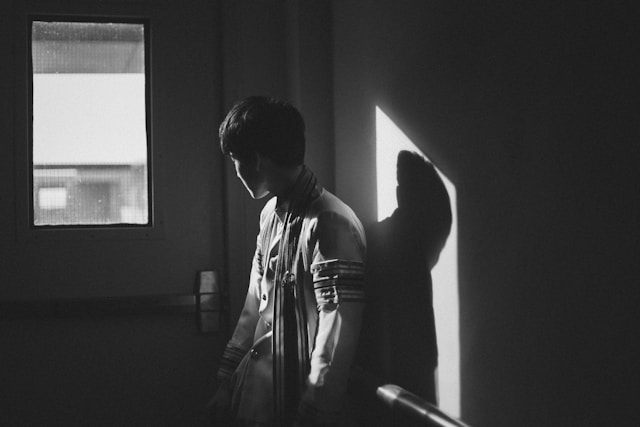
『14歳の君へ どう考えどう生きるか』(池田晶子著)で、「個性とは何だろう?」という問いかけがあり、それは本当の自分のことではないだろうかと説かれていた。
本当の自分が何かわかれば、自分の個性も判明するというわけだ。そこで著者は本当の自分とは何かということを突き詰めていく。
著者の結論としては、以下のような見解になった。
自分でどうこうしようとしなくても、おのずからその人は、その人がその人であるところの人になる。そういう「自分」が、すべての人には必ずあるんだ。それが本当の意味での「個性」なんだ。「みずから」ということと「おのずから」ということは違うんだ。「おのずから」は、自分の意図によらずに自然にそういうふうになることだ。君は、おのずから、そうなる人になればいい。みずからなろうとなんかしなくていい。そしたら君は、必ず個性的な人になる。
著者は、自分探しなどしなくても、ありのままの自分でいればいいという。「本当の自分とは?」とか、「自分の個性とは?」などと思い悩まなくても、自然のままの自分が本当の自分で、それが個性だという。
私は著者の考え方に触れて、宝物を探して深い森の中へ導かれたら、あちこちさまよった挙句、そのまま森の入口に戻ってしまったように感じた。
「本当の自分」「自分の個性」という宝物を探して森の中を探し回ったら、「その宝物はこんなところで探さなくても、君はもう持っているから帰りなさい」と言われて森から帰されたような気分だ。
自分の中にあるよと言われても、それがわからないから求めて行ったのに。あるがままの自分が本当の自分だと言われても、あるがままの自分がわからないから教えてもらいに行ったのに。
そこで私は、仕方なくまたその森の中へ入って行くしかなかった。
「我思う、ゆえに我在り」が本当の自分か?
著者の見解の土台にあるのは、デカルトの説く「我思う、ゆえに我在り」という、自分の存在を保証する最低条件だと感じた。
自分が考えたこと、例えば「本当の自分とは?」や「自分の個性とは?」などで得られるものは不確かなもので、確かなのは考える主体としての自分の存在だけだと説いているように思える。
考える側の自分だけが確かな存在であって、考えられた物はすべて不確かなものだということ。
もっと突き詰めると、考えた物は重要ではなくて、考える行為が重要なのだということ。私はそのように解釈した。
「考える自分」が本当の自分であって、「考えない自分」は本当の自分ではないという方向に私の解釈は進む。
では、「考える自分」と「考えない自分」とは何だろう?
「考える自分」と「考えない自分」
「考える」とはどういうことだろう? また、「考えない」とはどういうことだろう?
私は「考える」とは、疑ってみるということだと思う。「考える」とは、当たり前だと思っていること全てについて疑ってみることだと思う。
反対に「考えない」とは、当たり前のことを疑わずにいることだと思う。
だから、「考える自分」とは「全てを疑う自分」で、「考えない自分」とは「当たり前のことを疑わない自分」ということになる。
全てのことを疑って得られる物が重要なのではなくて、全てを疑う自分が存在することが重要だという点が肝心なのだ。
「自然な自分」、「ありのままの自分」といわれても、私にはよくわからない。周囲からの影響で、そういう意味の自分は変わってしまうからだ。
変わってしまうのは、考える自分、疑う自分の、考え方や疑い方次第で変わってしまうという意味だ。
だけれど、「考える自分」、「疑う自分」だったらイメージできる。周囲のことだけでなく、自分自身をも疑う自分なら確かな手応えを感じるのだ。
「自然な自分」、「ありのままの自分」を対象として見つめる側の自分、「自然な自分」、「ありのままの自分」を対象として疑う側の自分が本当の自分。そういうことも著者は説きたかったのではないかと思う。
「我思う、ゆえに我在り」で保証された自分の存在。保証されるのは我が思うから。思わない限り我の存在は保証されない。
本当の自分とは、考え、疑い続ける自分としかとらえられないものなのだということなら、私は理解できる。
「自然な自分」、「ありのままの自分」なんて、私にはまったくわからない。永遠に正体不明だ。でも、「自然な自分」、「ありのままの自分」とは何だろうと考え、疑っている自分なら、確かに自分なんだと思える。
参考文献:


コメント